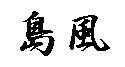
北海道ツーリングストーリー

4
ヨシエのいた夏
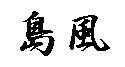
北海道ツーリングストーリー

4
ヨシエのいた夏
| 自分が今、体験していることは果たして事実なんだろうか。考えれば考えるほど頭が痛くなってきた。とにかく気を取り直そう。疲れてるんだ。ターミナル近くで、レンタルバイク(スクーター)をチャーターし、アクセルをあげる。そして、屏風岩、観音崎展望台の絶景を楽しんだ。素晴らしい眺めだ。海が蒼の基調をなし、草木の碧が見事に映えていた。 バイクに戻ろうと歩き出すと年輩の夫婦が植物をもぎ取っていた。盗掘か。希少な固有種を盗み生態系を壊す最低の行為だ。礼文島ではその被害が深刻だと聞くが、ここ天売島でも平然とやっている輩が存在していた。 「すいません。初めてです。以後は絶対にしません」 夫婦は俺をパトロール中の監視員と勘違いしたらしい。イエローコーンの赤十字入りの帽子と軍用のジャケットを着ているから間違えられても仕方ないか。 『あんたら、いい歳してふざけた真似してるじゃないか』 思わず怒鳴ると夫婦は、こそこそと逃げだしていく。こういう連中に限って、今の若い者はどうだとか一丁前なことを抜かすのだ。 ”だったらさあ、爆竹で威かしてやるなんて名案だと思わない?” なんだか耳元から女の声がまた聴こえだした。 『さっきから何者なんだよ。そんなにひどいことを思いつくなんて?』 俺はジッポで煙草に火を点けたついでに常備している熊避け用の爆竹一束へも着火し、放り投げた。 パン、パン、パパ〜ン・・・ 凄まじい轟音が周囲へ鳴り響く。すると驚愕した夫婦は同時に転倒し、腰を抜かして泳ぐようにもがいていた。ひどい。あまりにもひどすぎる。だが俺はちょっぴり映画ダイ・ハード2のエンディングの気分を味わっていた。 港に戻り、丁度出航するところの高速船に乗り込み天売島の余韻にひたった。空と海の鮮やかな青と草木の緑の世界。まさに天を売る島「天売島」。陸上と海上からばっちりと景色を堪能できた。北海道の旅の穴場だろう。 羽幌に到着し、宿へゼファーを引き取りに戻る。オーナーにライダー名鑑用の写真を撮っていただくが、それよりも確認したいことがあった。俺が泊まった日の宿帳だ。手を震わせながらページをめくると・・・ ヨシエの名前がない・・・ オーナーに確認してもそんな人は泊まってないという。これはどういうことだ?とにかく礼をいってマシンのアクセルをあげる。目的地は朱鞠内湖。ここでキャンプする予定だ。やや苫前へ引き返す格好でR239へ入る。いいワインディングが続く。でも頭のなかは、ヨシエの謎のことで一杯になり、走りにまったく集中してなかった。 霧立峠付近だった。大きな右コーナーをバンクしていると突然視界に・・・ キタキツネだ! 俺は根っからの旅系ライダーなので、極端にスピードを出すことはないが、バイクにはかなり乗れていると自負していた。たいがいの場面でも転倒はまずあり得ないと思う。限定解除も大型免許が教習所で取れない時代、つまり合格者数パーセントの超難関といわれた一発試験組(ちなみに2回目で合格)だ。ゆえにバイクの腕にも、それなりの自信(安定性という意味で)を持っていた。 でも、やはり今日は集中力に欠けていたとしか言いようがない。フルバンク中にフロントブレーキを思い切りかけてしまった。マシンと俺はアスファルトを勢いよく転がり滑っていった。 『やっちまった』 俺は、ゆっくりと上半身を起こし、ジャンバーやズボンについた汚れを手で叩きながら立ち上がった。 『あれ、ここは?』 ふとあたりを見渡すと今までよく晴れていたはずなのに薄暗いし、ここは霧立峠じゃない。そう、霧がかった海岸のような気がした。ほんのりと磯の香さえも漂っている。まさか焼尻の海じゃないだろうな? 「大丈夫よ。あなたは柔道経験が長いだけあって、やっぱり転び方も上手だわ。絶対に致命傷にならない転び方をするし。わたしも柔道をやっておけばよかった」 忽然とその姿を現したヨシエに俺は仰天してしまう。 『ヨシエ、おっ、おまえ、いったい』 俺は、なにをどう訊けばいいかわからないぐらい取り乱していたに違いない。 「いろいろごめんね。隠すつもりはなかったの。本当のことを知ったらかなり驚くと思ったから。でももう時間がないわ」 『時間がないって?』 俺はキツネにつままれているような感じがした。 「羽幌の宿の近くに大きなホクレンのスーパーがあったでしょ。運がなかったのね。焼尻島へ向かう途中、あの付近で事故に巻き込まれちゃって。わたしね、そのままずっとあのあたりから出れなくなっちゃったの。なぜか封印されていたみたい。あなたが焼尻に連れてってくれるまでは」 ヨシエは小さくため息をついた。 『宿には確かにいたよな』 「いたわ。けど、羽幌の宿のオーナーの記憶から、わたしは消えているわ。焼尻の民宿の老夫妻の記憶にもない。あなた以外に関わりがあった人は、誰もわたしのことを覚えてないわ。そういうルールになってるみたい」 『ルールって、誰が決めたんだ』 「わからない。そういうふうになっているとしか説明できないわ」 あまりにも衝撃的な事実の反動のせいか、こんな場面で俺は妙に落ち着いてしまった。 『俺に霊感はないはずだ。なぜ俺に憑いた?』 「さあ?なんででしょう。もっと若くてカッコいい人にすればよかったかな?」 ヨシエは軽く微笑んだ。 『ひでえ・・・』 思わず俺も吹き出した。 「強いていえば波長かな。どうやら羽幌へあなたがやってきて、わたしの封印を解くように決められていたみたい。前世、あるいは後世でなにか縁があると思うの。もしかしたら夫婦とか恋人だった気がする。だから、あなたならわたしのことをきっと理解してくれると確信したの。実際、今だってキツネぐらいで自爆しちゃうお人よしだから。でも霊感のないあなたの前に姿を現すのって、とってもエネルギーが要るのよ。天売でまで、ずっとあのまま傍で姿をさらけ出す力はなかったわ。点々としか登場できなかったの。つまり電池切れ寸前という感じ」 『そうか、それでわかった。天売でのおまえは幻じゃなかったんだな』 「憑きものは、憑いている人が動けばついてゆくだけだもん」 ヨシエは静かに笑った。 「でも、ここでお別れ。わたしは、これから遠いところにひとり旅にでるの」 『どこへ』 「本来、わたしが居るべき世界よ。ようやく、わたしのこと厄介払いできるね」 『そんなことより、ひとりで大丈夫なのかよ?』 「もう大丈夫。あなたに会えてようやくこの世の呪縛から解き放たれたの。やっと旅立つことができるわ。ちょっぴり未練はあるけど」 ヨシエはうつむきながら、なにかを考えるような素振りをしていた。 「あのね、あなたにお願いがあるの」 『なんだ?』 「あなたホームページで旅日記書いてるでしょ。でもわたしとのことは3年間内緒にしてね。3年過ぎたら描いて。おそらくそんな記事を信じてくれる人は少ないとは思うけど、この世にいた証ぐらいは遺したいわ」 『正確には、旅日記なんていうほどの几帳面なもんじゃないんだ。格好よく言えば旅の読み物。感性のない人が読めば、ただの雑文だぜ』 俺はやや自嘲気味に笑った。 「やだ、あなた、なんにも知らないの?」 ヨシエは、不思議そうに俺の顔を見つめていた。 『なにが?』 「あなたの旅の文章を読んだ人への魔力というか、どれだけ多くの北の大地を旅するライダー、いえ、旅人に多大な影響を及ぼした事実をご存じ?」 『知らねえよ、俺は他人のことまで関知せん。俺は俺で好き勝手に旅してるだけだもの。あんまり文学的でない北の旅の記録というやつは付随してきたのみだ』 「わたしも影響を受けたひとりだったのに!ふん、わかったわ。もういい」 怒った、いや呆れたという顔で彼女は呟く。 『しかし、なんでまた3年間なんだ?』 「向こうまでは近いようで遠いわ。ここの世界の暦なら間違いなく3年の長い旅路になるの。もう当分会えないけど、向こうからあなたの記憶のなかのわたしの姿を最初にゆっくりと見たい。その頃には、あなたの読み物も一段と風韻を帯びてくるでしょう。さらに、これからも続く一連のハプニングの真相も解明できるわ」 『一連のハプニング?なんだそりゃ?』 「今はいえない。いろいろ面倒ばかりかけてごめんなさい。でも、きっとあなたなら、わたしができなかった後始末をきっちりとつけてくれると信じています」 『おい、後始末って?』 なんだか、さっぱり言っている意味がわからない。だが時間のない彼女から、俺にとてつもなく重大ななにかを託されたような気がした。 「ねえ、わたしが、この世で生きていた意義ってあった?本当はね、不治の病に罹って、男に捨てられ、信じていた者に裏切られ、最期は若くして交通事故に巻き込まれておしまい。不幸を絵に描いたような、なにひとついいことのない人生だったのよ」 『あのな、世の中に意義のないことなんてないんだよ』 「本当?」 『おう、もちろんだ。俺がな、旅に出て、こうしておまえさんと出会えたことだって充分有意義なことだと思うよ。それに・・・』 「それに?」 『人の命には必ず終わりがやってくる。けど、終わりがあるから悲しいわけじゃない。旅と同じで終焉があるからこそ美しいのだ。今のおまえさんは、最高に輝いているよ』 「嬉しい。あなたって、いい人ね」 『ああ、よくいわれるよ。でも、その先のことをいわれたことは滅多にない』 「もっと早く・・・生きているうちに会えれば、その先の言葉がいえたかも知れない。残念だわ」 彼女は少し寂しげに微笑んだ。 やがて、ヨシエの体は、陽炎のように揺れだした。 「そろそろかな。なんだか怖いの」 『しかしなあ、幽霊のおまえにも怖いものがあるんだ?』 「あたりまえよ。わたしがこの世から消えてなくなるなんて信じられないわ。それまで手を握っていてくれる」 『わかった。いつの日か俺もそっちの世界にいくことになるだろう。それまで向こうでおとなしく待ってろ。なにも心配すんなよ。最後の瞬間まで俺は傍にいるからな』 ヨシエの右手を握った刹那、まるで電流に触れたような激しい衝撃がはしった。 『わっ、ヨ、ヨシエ、これはなんだ?』 パチパチと火花まで飛んでいる。もの凄いパワーだ。 「いずれ、わかる時がくるわ。あなたに、わたしの一部をあげたの。あなたには、まだまだ時間があるわ。わたしの分までたくさんこの時代の旅を楽しんでね。あと、あんまり飲み過ぎないでよ。これからは難しくて嫌な時代になるばっかりなの。人がよいぐらいじゃ、とても生きていけなくなるわ。あっ、ごめん。もう会えなくなるかと思うと、つい言葉が辛辣になっちゃって」 ヨシエの瞳から、滂沱と涙が溢れだした。 『大丈夫、俺はな、こう見えて存外したたかなんだ。なんとか生きていけるよ』 彼女は、肩を震わせながら泣いている。 俺は左手でハンカチを手渡した。 「ありがとう。あなたのハンカチって焚き火の匂いがするわ」 次第に薄れゆく輪郭の中で、ニコッと、とっても清々しい表情で彼女は微笑んだ。ヨシエの笑顔に俺はなにもかもが救われた気分になった。薄幸な短い生涯だったかも知れない。でも、おまえは間違いなくこの世に存在したんだ。俺なら確実に証明できるし、その軌跡は永遠だ。3年後に、ヨシエのいた夏の真実を俺なりにストーリー化してみせよう。 ヨシエの姿は、どんどん透明になっていく・・・ 「わたしのこと・・・」 『ん?言い残したいことがあるのか?』 「忘れないでね」 『あたりまえじゃないか』 俺の目からも熱いものが次々に込みあげてきた。なんとも形容し難い悲しい涙がぽろぽろとこぼれ落ちる。 「さよなら、北のサムライ・・・」 『気をつけていってこい、ヨシエ』 俺の掌から、ヨシエのぬくもりがなくなっていく。 ヨシエの掌の感触が完全に消えたころ、俺はハッと我に帰った。ひょっとしたら気を失っていたのかも知れぬ?ただね、ここは海岸ではないと確信した。強い真夏の陽射しが照りつける霧立峠だ。間違いない。ずいぶん長い時間、ヨシエと話していた気もするが一瞬だったような感じもする。 足元には、俺のハンカチとイチイの葉が1枚だけ落ちていた。ハンカチからは、なぜか潮風の香が微かに漂っていた。 「大丈夫だったかい?なんなら手伝うよ」 反対車線へ通りがかりの軽トラが停まり、車窓から顔を出した善良かつ呑気そうなオジサンの声が聞こえた。 『ありがとうございます。でも平気ですから』 幸いマシンも傷が少しついた程度だ。俺もかすり傷だけだし。 俺はその場で手を合わせ深々と黙礼を済ませ、静かにマシンを走らせた。すると一匹のキツネが道路わきを俺とすれ違うかたちで、てくてくと峠を降っていた。さっきのキツネかな?俺の姿をチラっと見たような気がした。 ヘルメットのシールド越しに広がる北の大地の空の色は、息をのむような圧倒的な蒼さであった。 |