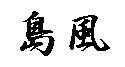
北海道ツーリングストーリー

ゴロタ岬
6
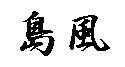
北海道ツーリングストーリー

ゴロタ岬
6
| 俺はリュックを担ぎながら強烈な砂の登り「砂走り」を黙々とよじ登った。すでに息はあがっている。後半は、何度も何度も休みながら登りきる。標高は意外に高くなり海が遠くに見えた。 延々と長い山道を突破し澄海岬を過ぎると礼文では珍しい砂地の海岸「ゴロタ浜」に至る。その付近には集落があり、民宿もいくつかあった記憶がある。とにかく今日はゴロタ浜付近で野営して様子を見よう。明日まで手がかりがなければ断念して島を離れるつもりだ。 とにかく歩いた。珍しくすれ違うグループがひとつもない。 途中、カロリーメイトや乾葡萄などで昼食をとっているとポツラポツラと雨が降り出してきた。くそっ、こんな時に。やがて本降りとなりガスも出始めた。 ここからなら、澄海岬を目指すより宇遠内に引き返した方が早いだろう。海が見える崖近くの一本道で、果て?どうしたものかとカッパを着ながら途方に暮れていると・・・ 人だ。人がふたりこっちに向かって歩いてくる。おそらく始点をスコトン岬に定めて元地あたりをゴールにした人たちにちがいない。 「こんにちは」 『こんちは』 すれ違いざまに挨拶をかわした。カップルだが彼女の方が酷く元気がない。かなり疲れている様子だ。すれ違って、ほんの数秒も経ったろうか・・・ 「きゃー」 悲鳴だ。振り返るとさっきのふたりのうち女性の方の姿がない。場所は俺がついさっき思案していた崖のあたりだ。 かっ、滑落だ・・・ 雨で足元が滑ったのだろうか。すぐに駆け戻った。ここは海抜30メートルはある断崖だ。まず助からないだろう。 『よせ、やめろ』 俺は叫んだ。カップルの男の方がリュックからロープを取り出し、近くの木へ巻きつけて躊躇わずに崖を降りて行くではないか。二重遭難になるぞ。男はどんどん岩を降りていった。 恐る恐る崖の上から下を見た。奇跡的に彼女は数メートル下の岩の突起した部分に引っかかっていた。そして男はその岩に辿り着き、彼女に声をかけていた。 『大丈夫ですか?』 俺は男に向かって大きく叫んだ。 「彼女は足をくじいた程度です。お願いがあるんですが、ぼくのリュックに短いロープがもう1本あるんで取り出してもらえませんか」 『分かった』 俺は崖の上からロープをゆっくり垂らした。 『どうする?救助を呼ぶかい』 「ここは携帯も圏外だし、あなたが救助を呼びに行ってもいつになるか分からない。それにこの岩自体がいつ崩落してもおかしくないほど脆い。大丈夫です。なんとかやってみます」 男は女性を背負い、ロープで自分の体へで固定した。 そして上から垂れているロープを握り、岩を登り始めた。無理だ。足場となる凹凸もない。ひとりならまだしも命綱一本で人間を背負い、垂直、いや、オーバーハング気味な崖を這いあがるなど狂気の沙汰だ。 思わずロープを引き上げようとしたら 「無理です。あなただけの力で崖の下にいる人間ふたりを上げられません。そのまま見ててください」 かなり余裕のある・・・いや百戦錬磨の経験からくる重みのある発言だ。自分が入り込む世界じゃないような気がした。 それでも俺は絶望感で目を覆う。目の前で2人も遭難する瞬間を見たくもない。 だが・・・ 驚異的な腕力だった。女を背負って少しずつだが確実によじ登ってくる。足場も脆いところを適切に避け、圧倒的なパワーで上へ上へと手が伸びてくる。凄い男だ。 『頑張れ、もう少しだ』 男のペースは終始同じに見えた。奇跡だ。俺はその瞬間に立ち会っている。絶対に素人の技ではない。一流のアルピニスト、いやロッククライマーか。 しかしロープを固定している木は地盤が弛んでいるせいか不気味にきしむ音を立てている。男が崖の上に足をかけた時、俺は右手を差し出した。左手は別の木にからませている。 バキッ・・・ 俺の手が男の手を握った刹那、ロープを固定した木が崖の下の海面へとまっ逆さまに落ちていく。まさに危機一髪だった。安堵感から俺は尻餅をついてしまった。 「本当にありがとうございました」 改めて握手をすると男は屈託のない微笑みを浮かべた。よく日焼けしていて白い歯が印象的な若者だった。 『いや危なかったな。俺はほとんどなにもできなかったよ』 「いえ、本当にあなたが居てくれて助かりました。じゃないと大変なことになるところでした」 謙虚で実に好青年ではないか。 『きみは素人じゃないだろう。山の経験とかかなり豊富そうだが』 「まあ、一応、道内の山岳会には所属していますが、まだまだです」 青年は照れながら謙遜したが俺は相当なもんだと確信していた。 「ところで、これからどこへルートをとりますか」 『この雨と霧だ。澄海岬を目指すのは自殺行為だ。宇遠内へ引き返そうかと思っていたところだ』 結構、時間も遅くなった。もうそうするしかないと思案していた。 「よかった。図々しいようなんですが、ぼくは足を痛めた彼女を背負って行きます。あなたには、ぼくの荷物を持っていただいてよろしいでしょうか」 青年は申しわけなさそうに俺に声をかけた。 『ああ、お安い御用だ。アバウトよ』 それより、彼女を担いでこれから元地まで歩くのか。改めて青年の強靭な体力に驚くばかりだ。俺も登山の経験はあるが30キロのリュックを担いで歩くのはよほどベテランで屈強のアルピニストじゃないと無理だ。ましてや女でも人一人担いでなら50キロ近いと思う。どこまでこの男は超人なんだ。 さらに雨や霧が強くなったなか、彼女を担いだ屈強な山男と俺は礼文の深い森の中を彷徨うように歩き出した。 |