北海道ツーリング夜話
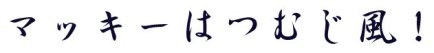
北海道ツーリング夜話
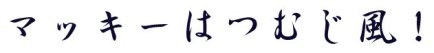

| 「最悪だ」 ゼファーのアクセルを握りながら呟いた。 とにかく酷い風雨だ。カッパにあたる雨粒がバサバサ激しい音を立てていた。オホーツクの海も大荒れだ。気温がそれほど低くないのが不幸中の幸いである。 宗谷岬を出発したときはまだ小雨だったのだが、村営猿払牧場を過ぎる頃、土砂降りとなった。オホーツク国道を走るライダーの数も少ない。空は墨を落としたように暗かったのだが、浜頓別に入るとなぜか雨があがり薄日まで差してきた。 『少し早いがこのあたりで野営するか』 たまたま通りにあったセイコマで買い物を済ませ駐車場で煙草に火をつけた。マシンに跨り携帯灰皿へ火を落としていると俺の前をライダー風の女性が、はっとするような爽やかな微笑を浮かべ丁寧にお辞儀をしていった。どっかで会ったか?いや記憶にないなあ。まあ、旅の社交辞令のお辞儀だろう。気にも留めず俺はスロットルをあげた。 クッチャロ湖畔キャンプ場、ここは道北で一番お気に入りのキャンプ場だ。湖畔の夕陽のロケーションが最高のポイントである。今日も期待に違わず絶妙の夕陽が湖面を真っ赤に染めていたが、つい先刻まで激しい雨が降っていたせいか人影はない。この風景を独り占めにできるとはとても贅沢なことだ。 さっさとテントを立てて焚き火台で炭を焼く。さて飯でも炊くかと思い、バッグのなかを探ると米が切れている。なんてこった。今夜は好物の塩ホルモンを肴に酒を飲んで寝ちまおう。 「こんばんは」 ウイスキーの封を切り一口飲んだ頃、後ろから声がした。振り返ると 「セイコマでお会いしましたよね。きっとここのキャンプ場を利用される方だと思いました」 『ああ、さっきの』 思い出した。セイコマの駐車場でお辞儀をくれた人ね。 「近くにテント張らせてもらってもいいですか。このキャンプ場はあなたしか居ないみたいですね。ずっと向こうのサイトにテントを張ったんですけどちょっと怖くて」 『どうぞ、でも俺の方が怖いかも知れないよ』 と言うと彼女は少し笑いながら頷き、消えていった。 暫くすると夕陽の中からCBXに乗った女性が現れた。随分と懐かしい粋なマシンだ。赤白のツートン、何を隠そう俺自身も昔乗っていたバイクだ。 『いいバイクに乗ってんだね』 俺は眩しげにCBXを眺めながら言った。 「ありがとうございます。わたしも気に入ってるんですよ」 にっこり笑いながら彼女はテントを立て始めた。俺は構わずウイスキーを飲み続ける。いつの間にか周囲はどっぷりと暗くなっていた。灯を入れたガスランタンが周囲を煌々と照らす頃、彼女は設営を終えて焚き火台の側へ現れた。 『飲むかい?』 ウイスキーのボトルを挙げると 「いただきます」 とマグカップを出した。 『俺はキタノだ。福島からだ』 「わたしは旅のなかではマッキーって呼ばれてます。さいたまなんです」 『さいたまのマッキーね。よろしくな』 とりあえず自己紹介を済ました。マッキーは、ちょっとぷっくらとした可愛らしい女性だ。童顔で実際の年齢よりかなり若く見える。 『お湯で割ると暖まるよ』 俺はマッキーのマグカップへお湯を注いだ。 「ほんと暖まりますね。北海道は夏でも夜は冷えますからね」 一口、グイッと飲んださいたまのマッキーの頬は真っ赤だ。 『でもね。夏の北海道ツーリングほど天候の当たりハズレが激しい土地柄もないんだよ。1999年などは、沖縄より暑い夏だったんだ。その年以降は冷夏が続いたけど』 「暑い?そんな年もあるんですか。わたしが彼と北海道に来た夏も寒かったんですよ」 と言ってマッキーはマグカップのウイスキーを飲み干した。なんか酒が強いみたい? 『あっ、今焼いている塩ホルモン、どんどんつまんでくれ』 「ありがとうございます」 マッキーはバクバクと食べ始めた。しまった。俺の夕食がどんどん減っていく・・・ そして、ついに塩ホルモンが消えた(涙) 「実は北海道を彼氏とふたりでキャンプツーリングに来たのは一昨年なんです」 ガブガブと俺の酒を飲みまくったマッキーが突然哀しい目になった。 『ほう、彼氏と婚前旅行ねえ。そいつはいいご身分だ』 あまりの子供っぽさに思わず吹き出してしまったが、俺もいい加減酩酊して来たぞ。 「キタノさん」 『なんだ?』 マッキーは思い詰めた顔をした。 「お腹が空きました」 ガクン・・・ 『あのな缶詰めくらいならあるが、あいにく米を切らしてんだよ』 俺は脱力感に覆われながら応えた。 「米とクッカーならあるんです。でも炊き方が分からないの。彼と別れた理由は彼の趣味のキャンプツーリングで、あまりにもわたしがなにもしないし、できないから愛想つかされたんです。全部彼がやってくれたし」 旅のなかでの身の上話かい。よくある展開だ。 『で?マッキーは覚える気があんの?』 「教えてもらえるなら」 なんか目眩がしてきた。 『まあ、万事アバウトのキタノ流でよければ喜んで伝授しよう。実は俺自身も数年前までなにもできなかったんだ。でも誰から学んだワケじゃない。旅のなかでの数限りない俺自身の失敗の連続から身につけた』 マッキーはえらく神妙な、いや真摯な目つきで 「キタノさんにもそんな時代があったんですか」 と俺の顔を見つめている。 『もちろん、誰だって最初はビギナーだよ。俺の場合はさらに不器用がつくが』 俺は米を洗い出した。 『いいか、クッカーに米と水を入れ、手で米を研ぐ(まわすだけ)。まめに水を入れ替えながら1合や2合程度なら100回も手をまわせばOKだ。米と水の配合は1:1.2だ。それが一番上手くいく。あとは最低30分ぐらい水につけておくと仕上がりがいい。これで第一段階終了』 俺は煙草に火をつけラジオのスイッチを入れた。やっぱりロシア語ばかりだ。 「意外に簡単そうなんですね」 彼女は目からうろこが落ちたような表情をしていた。 「もっと早く覚えていれば彼と別れることもなかったのに」 そして溜息をついている。 俺はゆっくり煙草の煙を吹き出し、あえてなにも言わなかった。 マッキーのお話しはさらに続く。 「彼はキャンプツーリングの達人で、料理はプロ並でした。わたしは彼と知り合うまでキャンプなんてしたこともなく興味もなかったの。料理も上手じゃないし。いつも彼がなんでもしてくれることについ甘えて見てるだけでした」 少し、風が出てきた。というより、つむじ風のようなものが吹き荒れている。マッキーの声が寒さのせいか震えて聞こえた。 「ある日、おまえはなんで少しも手伝おうとしないんだと怒りだしたの。それ以来、少しずつ気まずくなりキャンプにも誘われなくなりました。そしてまったく会わないようになり数ヶ月が過ぎて、別れようとメールがきて、それっきり・・・」 マッキーは涙ぐんでいるらしい。 「彼への未練だと思うんですが、キャンツーだけは続けてますけど。キタノさん、どう思います?」 『俺もあんたの彼と同じだね。怒るよ。キャンプに来てなにもしないで見ているやつは男だろうが女だろうが一緒に野営はしたくない。なんでもいい。自分のできる簡単なことでいいから手伝わないと。手伝おうとしないと』 マッキーはうつむいてしまった。 おっと30分以上過ぎたな。 『マッキー、萎んでないでよく見てな。このままバーナーで弱火の中火で炊くだけだ。水蒸気が出て水気が完全に抜けるまで炊くんだ』 やがて水気が抜けてきた。 『こっからが肝心だぞ。米が焦げるか焦げないか微妙な匂いがしたら火を止める』 「そんな微妙な匂いなんてわかんないわよ」 マッキーは怒ったような口調になった。 『いいから、煙の匂いを嗅げ』 俺はニヤニヤしながら指示した。 『いまだ!火を切れ』 マッキーは、びっくり眼でたどたどしくバーナーの火を止めた。 『どうだ。匂いのタイミングが分かったか』 「分かるワケないじゃん。そんな微妙な匂い」 ツッケンドンな言い方だ。 『水蒸気が消えてから集中して匂いを嗅いでいれば必ず分かる。そしてアバウト15分、蓋を開けずに蒸らす』 「そんなに簡単にクッカー炊きができるの?」 『まあ、待ってろ』 俺はウイスキーをゆっくりと飲んだ。 『そろそろかな。マッキー、蓋を開けてみなよ』 マッキーはクッカーの蓋を恐る恐る開け始めた。 すると・・・ 「スゴーイ、カニの穴まで開いている」 マッキーの瞳は爛々と輝いていた。 「美味しそう。これならわたしにだって絶対に出来そう」 マッキーは上機嫌で歓声をあげた。 「うん、美味しい」 マッキーは俺が提供した缶詰をおかずに忙しく箸を動かしていた。 『ほかほかご飯のおかずは豪華じゃなくてもいい。なんにでも最高に合うんだよ』 「本当ですね。こんなに美味しいご飯初めてです」 『さらに野外というシチュエーションが最大の調味料になるからな』 俺もご飯を飲み込んだ。 「これだけ教われば炊き込みご飯とかいろいろ応用が効きますね」 マッキーはにこにこしながら言った。 『たいへんよろしい』 この一言は本当に嬉しかった。教えた方にも教え甲斐がある。後は俺から学んだ基本的なことをどんどん応用してくれ。旅人は創意工夫が真髄だというのが俺の持論だ。 「ご馳走様でした。そろそろ休みます」 マッキーは自分のテントに戻ろうとした。 『ちょっと待った』 マッキーはポカンとして振り返った。 『クッカーに水を入れとけ。そして明日の朝、湖畔の砂でクッカーを洗うとこびりついた取れ難い米がきれいに落ちる』 と俺が言うと 「ありがとうございます。そうします」 彼女は素直にクッカーへ水を入れてから自分のテントのジッパーを閉めた。 翌朝、小鳥のさえずりで目覚めた。 寝過ごしたか。旅のなかの俺はいつも早起きなんだが、珍しく寝坊したようだ。 ジッパーを開け外へ出ると一片の雲もない好天だ。 マッキーは?マッキーのテントがない? 「おはようございます。キタノさん」 マッキーは既にテントの撤収を済ませ、CBXへのパッキングも終了していた。 「本当は昨夜教わったクッカー炊きで朝食をご馳走しようと思ったんだけど日程的に急がないとマズイんですよ。これで朝食を炊いてください」 ビニール袋に入った米を渡された。 『あっ、ありがとう』 俺は呆気にとられた。 「お礼を言うのはわたしの方です。本当にいろいろありがとうございました」 マッキーの顔は、本当にすっきりとしていた。 「また会えますよね」 『ああ、夏に北海道をキャンプツーリングしてれば、きっとね』 「キタノさん、また会える日までお元気で。次はわたしがご飯を炊いてご馳走します」 童顔のマッキーは、実に可愛らしい笑顔でクッチャロ湖畔キャンプ場を旅立って行った。 翌年・・・ 俺は毎年恒例の夏の北海道キャンプツーリングを決行していた。 俺の道東のベース基地「和琴キャンプ場」へ到着する。ここはライダーに人気のあるサイトなのでとても混み合っていたが、なんとか僅かなスペースへテントを立てウイスキーを飲みだした頃・・・ 「水気が完全に切れてから、焦げるか焦げないか微妙な匂いがしたらバーナーの火を止めるの。なにやってんの。まだ早いでしょう。旅人は創意工夫なのよ」 俺のテントの裏に張ったカップルの彼女の声がうるさい。 「わたし自身も去年までなにもできなかったの。それでも失敗の連続でキャンプの技術を身につけたわ」 どっかで聴いた声だ。 もしかして・・・ さいたまのマッキー? 間違いない。 『マッキーだよな。俺だ。キタノだ』 と声をかけた。 「師匠スか?キタノさん?」 『おう、久しぶり。新しい彼氏か?』 「違うの。一緒に飲もうって、この子が声をかけてきたの。ナンパするならご飯くらいご馳走しなさいって言ったら、クッカー炊きをしたことないって言うじゃないの。もう信じられない。だからまず米の炊き方から教えてたの。女を覚えるのは百年早いわ」 その軟派野郎はしょぼんとしていて惨めに見えた。逆にマッキーは童臭が消え、大人っぽく美しいお姉さま系へと逞しく変貌していた。 『おまえ、いい女になった。いや、女振りがあがったよな』 「そんなあ〜、からかわないでくださいよー」 マッキーの頬がちょっと紅く染まる。 俺も炊きあがったご飯をご馳走になった。確かに美味い。 でも軟派野郎は 「こっ、これでぼくは失礼します」 熱いご飯をよく噛み締めもせず、ほとんど飲み込みながら食べ終えた。 そして逃げるように自分のテントへ這い戻った。さらに地面まできっちりとジッパーを閉め、それっきり外に出て来ない。テントの中で震えているんだろうなあ、きっと。あの食べ方じゃ口の中を火傷したんじゃねえか? 『可愛そうに。ナンパした相手がまずかったな・・・』 俺はなんだか軟派野郎へ同情してしまった。 女キタノ(マッキー)は 「キャンプに来てなんにも出来ないやつって最低ね。まだ水を入れてクッカーをうるかす作業が残っているのに情けない男だわ」 と気炎をあげている。 そのとき、和琴湖畔キャンプ場へ一陣のつむじ風が舞い、俺の唇からくわえ煙草が落ちた。彼女に会うと必ず突風が吹きつけてくる。 マッキーはつむじ風・・・ |