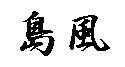
北海道ツーリングストーリー

最終章
さらば、もうひとりの北のサムライ
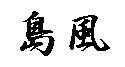
北海道ツーリングストーリー

最終章
さらば、もうひとりの北のサムライ
| ヨウスケはじっと焚き火を見つめていた。 「ヨシエ、本当にすまん。ぼくが全部悪い」 『・・・・・』 思わぬ人物の名がここでヨウスケの口から出てきた。でもまさか?偶然だろう?確かヨシエは神奈川県出身だったはずだ。 『ヨウスケ、おまえの彼女の名前は、ヨシエっていうのかい。もともと稚内の人なのか?』 「カナ、ヨシエの姉妹は何年か前、父親の仕事の関係で神奈川から稚内に移り住んで来ました。ヨシエが稚内から札幌の大学へ入学した年の帰省中に知り合ったんです」 間違いない。なんだか話がこういう展開へ進むと俺が誰かの筋書きの上を歩いているような気がしてならない。 『そのヨシエさんが事故に遭ったっていう場所は、もしかしたら羽幌。焼尻に向かう途中じゃないのか?』 「なぜ知ってるんですか。カナから訊いたんですか?」 『いや、カナから訊いたわけじゃない。間違いなくヨシエ本人から訊いた。つい先日までヨシエと一緒に行動していたよ。まあ、これも相当不思議な話なんだが』 俺は焼尻、羽幌そして霧立峠であったすべての出来事を克明に話した。 「あり得ない。そんな悪質な冗談はやめてくれ。いくらあんただって絶対に赦さないぞ」 ヨウスケは声を荒げた。 『繰りかえすようだが、俺はカナから依頼された頼みごとを遂行したまでの旅人だ』 「大きなお世話ですよ」 この言葉を耳にしたとたん、俺は怒りで頭が真っ白になりヨウスケを思わず殴り飛ばしていた。 『甘ったれるなよ、若造が。俺の話を信じるも信じないも自由だ。ただな、ヨシエは霧立峠でなにもかもふっきれた、本当にすがすがしい笑顔で旅立って行ったよ。そんなヨシエが俺はあまりにも不憫でならん。それに俺の話が即興の作り話でできる範疇か。少しは自責の念でおかしくなっているカナのことも考えたらどうだ。カナは稚内で、おまえの帰りをひたすら待ち続けているだけの可愛そうな女なんだよ』 それっきりヨウスケは黙り込み、俺はツェルトに入り横になった。 翌朝、ツェルトから這い出るとやはり霧で視界ゼロの光景であった。でも、微妙に陽が射してきている。きょうはこれから間違いなく晴れると思う。ヨウスケは火の消えた焚き火の前で黙然と座っていた。どうやらあのまま夜明かししたらしい。 『おはよう』 ヨウスケに声をかけても頷いただけだった。頬には俺から殴られた痣が痛々しく残っている。 やり過ぎたかもしれない。でもヨシエやカナのような女性は男として絶対に守ってやらねばならないし、純真な女を泣かせる行為だけは間違いであると思った。 陽光で視界が確保できるようになった頃、ようやく腰を上げ出発した。ヨウスケはエミを背負ったまま一言も口を開かず黙々と歩いている。ペースが異様に早かった。なにかから逃れたいような歩調である。 砂走り頂上付近へ到達。ここまで来れば宇遠内はすぐだ。強烈な降り、エミを背負ったヨウスケも流石に慎重に下降していく。もちろん後に続く俺も足元を確認しながら一歩一歩確実に降りたつもりだったが・・・・ ズサッ・・・ 滑落だ。足場にした岩がぬかるだ土壌で崩れ、バランスを失った。俺は東側の斜面に勢いよく転げだす。あちこちに体をぶつけながらどんどん落ちて行く。俺はこのまま滑落死するのか? 大きな枯れ木にリュックをぶつけ俺の体はようやく止まった。リュックがクッションとなり致命傷は免れたらしい。指、腕、足を順番に動かして行く。あちこち痛いが骨には異常がないようだ。 「大丈夫ですか」 ヨウスケの声だ。 「今、そっちに行きます」 『ヨウスケ、俺は自分でなんとかするから来なくてもいい』 言い終わる間もなくヨウスケはエミを背中から降ろし、一気に下降してきた。その姿は実に躍動的で鮮やかなものだった。瞬時に安全な足場を確保しながら絶妙のバランス感覚で動いている。感動的、いや劇的なこの瞬間を俺は終生忘れることはあるまい。そして、あっという間に俺のところへ到達してしまった。 『本当に大丈夫だ。骨にも異常がないようだし』 既に立ち上がっている俺にヨウスケは右手を差し出した。握手を求めているようだ。俺も手を出すとガッチリと握った。 「昨夜は取り乱してしまい失礼しました」 ヨウスケは、透き通るような素晴らしい笑顔を見せた。 「昨夜、キタノさんが寝た後、いろいろ考えました。ぼく、稚内のカナのところへ帰ることにします。夕べの話で、それがヨシエの意思だと確信したからです」 『そうかい。それが一番いい。ヨシエはな、たぶん、これからのヨウスケだけを気がかりにしていたんだ』 俺は心から嬉しく、そして優しい気持ちになれた。 「キタノさんの大事な旅をぼくら3人のことで、メチャメチャにしちゃったようで」 『いいんだ。アバウトだよ』 「あの、ひとつ訊いていいですか」 『ああ、なんなりと』 「ヨシエのやつ、もしかしたらキタノさんに惚れてませんでしたか?」 ヨウスケは敏感になにかを察知している様子だ。 『馬鹿かおまえ?俺は既婚だぞ。それに昔から、そういう機微には無頓着だったから知らないね』 「失礼な質問をしてすみませんでした。あなたは、いい人ですね」 『ああ、よくいわれるよ。でも、その先のことをいわれたことは滅多にない』 なにもかも得心したように彼は苦笑いしていた。 そして、ベルトからよく手入れされた和式ナイフを外し、 「ぼくにはなにもないけどこいつだけが唯一の自慢なんです。ずっと山行を共にしてきました。親父の代から使っている物です。何度も砥ぎながら藪漕ぎや薪割りなどで酷使してきたので刀身がかなり痩せてますけど。お詫びのしるしにどうかもらってやってください」 と、手渡された。 |

| 実は昨夜から気になっていたナイフだった。よく見ると”レッドオルカ”ではないか。しかも甲伏せ造り(日本刀と同じ製法)1尺、選ばれし”天神”の刻印が刻まれた究極の土佐剣鉈だ。まさにマニア垂涎の一振りであり、実戦剣鉈の最高峰だ。こんなに高名な大業物、さらに父親の遺品でもある和式ナイフを自分が頂戴するわけにはいかぬ。俺はもちろん固辞した。 「いいんです。こんな使い古しの剣鉈なのですが、あなたのこれからも長く継続する北海道の旅の中でお役に立てる場面がいつか必ずやってくるはずです。こいつさえ握っていれば勇気が湧き、どんな困難でも克服できるのです。北のサムライの旅の護刀”レッドオルカ”、どうか永く正しく使っていただきたい」 とうとう押し付けられてしまう。名刀だからというよりもなんだかヨウスケ本人の形見をもらうようで実は気が引けていたのだ。 『ヨウスケ、とにかくどんな登山でもダメなときはきっぱり諦めて帰って来なさい。勇気ある撤退も必要だよ。俺はね、登山家ではないが、旅人だ。体は張っても絶望的な無理だけはしないようにと心がけている。カナさんをこれ以上悲しまさんな』 「もちろんですよ。ぼくも生きて還った人が最大の登山家であり冒険家だと思ってます」 彼は力強くうなずいた。 海岸のゴロタにとりかかった頃、強い陽射しが照りつけてきた。俺は腕で顔の汗を拭いながら煙草に火をつけ、ヨウスケに話しかけた。 『無敗の王者よりも強いやつっているもんなんだよ。敗退、挫折、失敗、屈辱を繰り返しながらも必ず這い上がってきて、最後まで生き延びるやつがな』 「キタノさん、もしかして自分のこと言ってるんですか」 ヨウスケは吹き出していた。 『そこまで自惚れてはいないが、そうありたいと思うな』 強烈なゴロタに息を切らせつつ答えた。 俺は山屋としてパーフェクトに近いヨウスケの未来へ暗い予感が芽生えていた。あまりにも若くして才気があふれ過ぎている。絶対に妥協しない燃えあがるような熱いオーラを周囲へ激しく放っていた。 このままではいずれ破滅してしまう・・・ だからこそ説教がましいオヤジみたいだと思われても一言釘をさしておきたかった。旅人キタノが他人へ、これほど干渉することはかつてないことだし、これからもまずあり得ないだろう。もちろん冬山はやめろなどというつもりはない。コタツで丸くなっているよりも俺は遥かに有意義だと思う。 けど矛盾するが、不器用な俺とはまさに正反対の万能・天才肌の男、これほどの青年があっけなく消えてしまうなんて、とてもじゃないが耐え難かった。 まあ、俺の考え過ぎなのだろう。宇遠内あたりで、自分のなかに芽生えだした悲しい予感を無理矢理打ち消した。 礼文林道で、最終地の元地に宿の車を停めているというヨウスケやエミと別れた。俺はベースキャンプを撤収し、島の玄関口である香深港へと向かう。フェリーの中でも俺はずっと考え続けていた。 結局、俺はヨシエの代わりに動いていたようなふしがある。いや、きっと動いていたんだろう。 俺は、ただ利用されていただけの間抜けな男だったのか? でも、そんな風には解釈したくなかった(これが俺の甘さなのだが)。これはこれで充分感慨深い旅になったではないか。今回の出来事も旅のひとつの断片だ。いろんなことがあってこそ、ひとり旅の醍醐味かも知れない。 稚内港フェリーターミナルは風が強かった。利尻山の方角から激しい島風が吹きつけていた。マシンにまたがり待合室に行ってみたがカナの姿は見えなかった。もうヨウスケから連絡が入ったのか? 俺は静かに宗谷岬方面へ向けスロットルをあげた。 やがて、オホーツクに鮮やかな夕陽が大きくゆったりと沈んでいく。 『ヨシエ、なにもかもこれでよかったんだよな』 北洋埠頭を眺めつつ、俺は機上で独りごちた。 『うっ、眩しい・・・』 刹那、バックミラーから陽光が反射し、とてつもない輝きが俺の顔面をとらえた。 なんだか、ヨシエの悪戯っぽい笑顔が思い浮かんだ。 マスモトヨウスケ その後のヨウスケの消息を知ったのは3年後のことだ。北アルプス穂高にて遭難。雪崩に巻き込まれてしまう。あれほどの体力、技術、経験をもった男でも圧倒的な大自然の気まぐれ「雪崩」の前にはなす術がなかったらしい。結局、父親と同じ運命を辿ってしまった。俺は愕然とし、目の前が真っ白になる。 でも心のどこかで、過去に予感していた悲しい結果になったとも気づいた。もしかしたら護刀レッドオルカを握ってさえいれば災難を回避できたのかもしれない。でもヨウスケなら、そんなことあるわけないじゃないですかと笑って否定するだろう。 俺は人の運命が予知できる。 どうやら、霧立峠での転倒事故以来、妙な能力がついてしまったようだ。ヨシエもヨウスケの運命に気づいていたのだろう。そしておそらく、ヨシエの持っていた超能力、もしくはパワーのようなものが俺の体内へ移入されてしまったらしい。 しかし、微妙であまりにも感覚的な現象なので詳しく口で説明することは不可能だ。映画でいえば「グリーンマイル」の後半のトム・ハンクスみたいな状況といえばおわかりいただける方が多いかも知れない。以降、俺の日常の中で次々と起こる不可思議な現象がすべてを証明した。 さらに彼女の体質の一部も俺の体内へ伝播していた。あれほど苦しんでいた船酔いの症状が完全に消えた・・・というより、むしろ異様なぐらい船旅に強くなった。もしかしたら彼女は、この世界にかつて間違いなく存在していたという証を俺のなかへ遺し、短いなりの生涯のストーリーを俺の読み物の中で完結させて逝きたかったのやも知れない。 「3年過ぎたら描いて」 ヨシエの言葉にすべてが起因する。 ヨウスケの運命を知っていたヨシエは、きっとこの旅のストーリーを二人一対、表裏一体で俺に描いて欲しかったのだろう。それが3年後なら、この不思議な旅の出来事のなにもかもが符合する。 「でもね、どんなに経験や技術があっても所詮人間の微々たる力で大自然には勝てません」 礼文の森の中でビバークしたとき、いみじくもヨウスケが俺に語った言葉を想い出す。 俺と礼文で別れた後のヨウスケは、その若い才能と実力が結実し、山岳誌等で喧伝されていく。次々とどんな過酷な条件の山へでも破滅的な闘志で挑んで行く勇姿から名づけられたニックネームは、まったくの偶然ながら”北のサムライ”だった。 ヨウスケはキタノとのニックネームの一致を無邪気に喜んでいたという。一番苦しいときに支えてくれた人物と同じニックネームになって嬉しいと対談記事にも掲載されていたそうだ。 この事実を知った瞬間、俺はまたも熱いものが込みあげてしまった。 ヨウスケは、厳冬期には人跡未踏の伝説のスラブ(一枚岩)へのクライミングにも最短時間で幾度か単独で成功を収めるなど既存の概念を覆す革命児でもあった。あたかも巨鯨に挑むオルカ(シャチ)の如く。そして、実力のある若者へ対するセオリー通り、頑迷で保守的なオヤジ社会からのイジメやジェラシー・妨害にも随分遭ったらしい。 それでも真摯に山行を愛し、彼一流の技術と屈託のない人柄を理解する多くの仲間たちへ囲まれていく。穂高にはスポンサーもつき遠征が決まっていたヒマラヤへの高度順化のために入ったとも言われている。ただ、若き彼の生涯が白銀の中で散華する瞬間になにを思ったのだろうか。 今となっては、もう誰も知るよしもない。 俺は夏になると、礼文の森で出会ったときの胸に沁みわたるような爽やかなヨウスケの笑顔がいつも鮮明に蘇えってくる。 さらば、もうひとりの北のサムライ。 そして、さよならヨシエ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 忘れないでおくれ 忘れないで 忘れないで この島のことを めぐり逢えた旅人たちの 子供のような眼を 野山を飾る花よりも 美しいものがある それは花に囲まれた 飾らない君の笑顔 忘れないで 忘れないで 忘れないでおくれ 忘れないで 忘れないで この島のことを 旅立つ船が見えなくなるまで ちぎれるほど手を振ろう 最果ての海の色より 澄んだものがある それは船のデッキの上で 手を振る君の涙 忘れないで 忘れないで 忘れないでおくれ どこかの街でまた逢おう 便りを書いてくれ 君のことは忘れないよ さよなら旅の友達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「キタノさんが、北海道で一番好きなところは?」 『ああ、躊躇いなく答えるね。誰がなんといっても礼文だよ』 3年後の猛暑の夏、俺は久しぶりに礼文林道へ入った。ベルトには名刀「レッドオルカ」と呼ばれる海内無双の和式ナイフがぶらさがっていた。 |